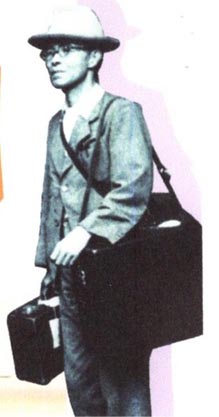町田佳聲の略年表
更新日:2026/1/6、掲載日:2025/8/1
町田佳聲(1888~1981)日本の民謡研究家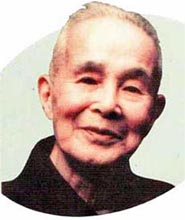 荒物醬油店の町田賢兵衛、タツの次男として、伊勢崎郵便局本局の道路を挟んだ南にある大きな二階建ての家(現三光町)で生まれる。 幼名は英(はなぶさ)。母タツは常磐津を親しんでいた。子どもの頃は体が弱く、いつも母タツといることが多かった。母が口三味線を混じえて歌っていた常磐津を聞いていたことが、英を邦楽に興味を抱かせることになった。 明治
大正
昭和
※1956年(昭和31年)紫綬褒章を受賞。 ※1962年(昭和37年)姓名学者から雅号「佳聲」(かしょう)が贈られ、筆名として使い始める。 ※1965年(昭和40年)勲四等・旭日小綬章を受賞。 ※1974年(昭和49年)勲三等に叙され瑞宝章を受賞。 【参考図書】 ・武内勉「民謡に生きる 町田佳聲八十八年の足跡」株式会社ほるぷレコード 昭和49年12月1日発行 ・「町田佳聲展」ぐんま民謡フェスティバル実行委員会 平成9年8月30日発行 【日本民謡大観とは】 NHK(日本放送協会)が戦前から約半世紀にわたり継続して刊行した図書で、日本各地の民謡をその土地の演唱者の協力を得て収集した民俗音楽資料です。採譜した楽譜、歌詞およびその歌の解説が記載されています。加えて、地域ごとにその土地の地理・風土・風習等の概説が付されています。 町田佳聲顕彰会
|
▲ページTopへ